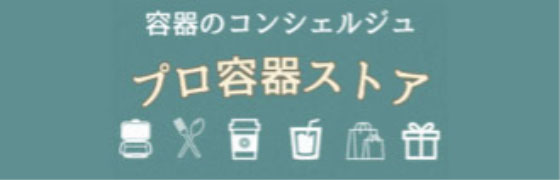コンビニでおしぼりをもらっても、つい使い忘れてしまう――そんな身近な存在が「紙おしぼり」です。
本記事では、紙おしぼりの歴史・種類・選び方を飲食店目線で分かりやすく解説します。
店舗のブランディングや顧客満足につなげたい事業者さん向けの実務ポイントを中心にまとめました。
おしぼりの歴史
諸説ありますがおしぼりの歴史は古く、「古事記」や「源氏物語」が書かれた時代まで遡ると考えられています。
- 起源:日本では古代(『古事記』時代)から濡れた布で客をもてなす習慣があったとされる。
- 江戸時代:旅籠で手ぬぐいが使われ、手や足を拭く文化が定着。
- 戦後〜昭和30年代:店が自前で布おしぼりを洗って提供 → 客数増加で貸出ビジネス化。
- 1970年代以降:使い捨ての紙おしぼり(不織布)が一般化。
そもそも紙おしぼりとは?
世界と比較すると日本は清潔に対する意識が高い国と言えます。
日本人の清潔意識の高さがおしぼりが日本固有の文化として根付いた一因と言えるかもしれません
紙おしぼりは一般に「使い捨ておしぼり」と呼ばれる不織布製品です。
主な特徴は以下の通りになります。
- 形状:平型(折り畳み)・丸型(ロール)
- 素材:パルプやコットンが原料の不織布・再生紙が原料の不織布・レーヨン(化学繊維)等
- 包装:ポリ袋などの個包装(宣伝印刷可)で提供
- 用途:テイクアウトの付け合わせ、店内のおもてなし、衛生用など

紙おしぼりの選び方
まず「目的」を明確にする
紙おしぼりを選ぶ際の基本は「何を達成したいか(目的)」を決めることです。
ほとんどのお店の最終目的は、お客様から「また行きたい店だ!」と思ってもらい、実際にリピーターとして定着してもらい、結果売り上げを上げることがゴールです。
その目的を果たすためにはまずお客様に与える印象が大切です。
ポイントを押さえて、賢く選ぶのがおすすめです。
以下のポイントを参考にしてみてください。
- 目的例:清潔感の演出/コスト抑制/高級感演出/携帯性重視
- 判断軸:素材感(手触り)、サイズ、包装形態、耐久性(破れにくさ)、単価
- オペレーション:保管スペース、スタッフの取り扱いのしやすさ、廃棄方法
用途別の具体案3つ
今回は3つのケースで、具体的にどのようなおしぼりを選んでいけば良いのか、ご提案させていただきます。
「安い・早い・美味い」テイクアウト重視の店
- おすすめ:ハーフサイズの平型(省スペース・コスト低
- 素材:破れにくいレーヨン混を選ぶと破損対応が不要で安心
- 運用:ロールや箱置きで在庫管理を簡素化
女性客向けの「リラックス空間」
- おすすめ:パルプ系のソフトタッチ製品・やや大きめサイズで包み込む感触
- 包装:丸型ロールやふんわり見えるパッケージで印象アップ
高級志向・富裕層ターゲット
- おすすめ:ガーゼ系や厚手の高級紙おしぼり・香り付きや個装デザインにこだわる
- 差別化:パッケージの素材を上質にするだけでブランド感が高まる
具体例を3つ挙げましたが、まとめると以下の3点が選ぶポイントとなります。
-

第一印象:
手触り・厚みで清潔感や高級感を演出できる
-

実用性:
破れにくさや拭き取り性能は顧客満足に直結
-

見た目:
包装・印刷でブランド性をアピール可能(ロゴ入れも検討)
紙おしぼりの選び方 まとめ
- 想定客層に合う素材とサイズを決める
- 保管場所と提供動線(手渡し/セルフ)を確認
- 一度サンプルで実際の手触り・破れ具合を確認する
- 印刷(ロゴ)の有無を検討
紙おしぼりは単なる衛生用品ではなく、最初に触れるアイテムのひとつで、店舗の印象を左右する接客ツールです。
まず目的を明確にして、サンプルで確認してから本導入するのが失敗しない秘訣です。
木村容器では各種サンプルをご提供可能です。ご希望の方はお気軽にご相談ください。
 オンラインショップはこちら
オンラインショップはこちらよくある質問(FAQ)
- Q1. 紙おしぼりと布おしぼり、どちらがコスパが良いですか?
- A. 使用回数や衛生管理の手間を考えると、回転率の高い店舗では「紙おしぼり」の方がトータルコストを抑えやすい傾向があります。布おしぼりは高級感や演出面で優れています。
- Q2. 紙おしぼりの印刷はどんな用途に向いていますか?
- A. 店舗ロゴやメッセージを印刷することで、ブランド印象を強化できます。特にテイクアウト・デリバリーでは販促効果も期待できます。
- Q3. 紙おしぼりの保管時に注意すべきことは?
- A. 高温多湿の環境を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。湿気があると品質が劣化する場合があります。
- Q4. 環境に配慮した紙おしぼりはありますか?
- A. 天然素材や再生素材を使用した紙おしぼりがあります。環境配慮型の製品は、企業イメージ向上にもつながります。
- Q5. サンプルを取り寄せることはできますか?
- A. 木村容器ではサンプルをご提供可能です。実際の手触りや厚みを確認してからご検討ください。※配送費用がかかる場合もあります
▶ お問合せはこちら